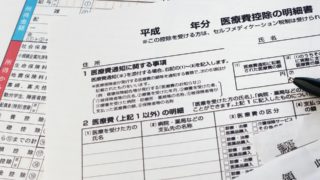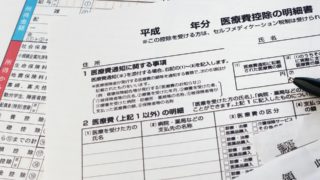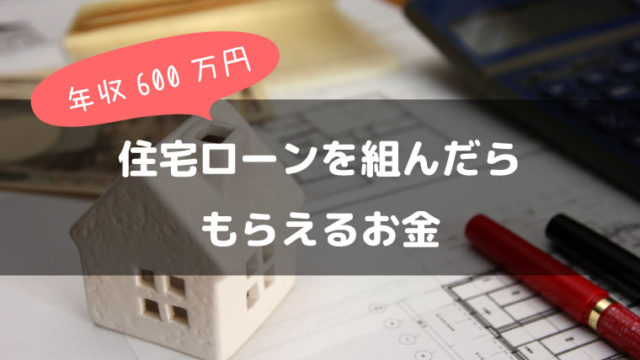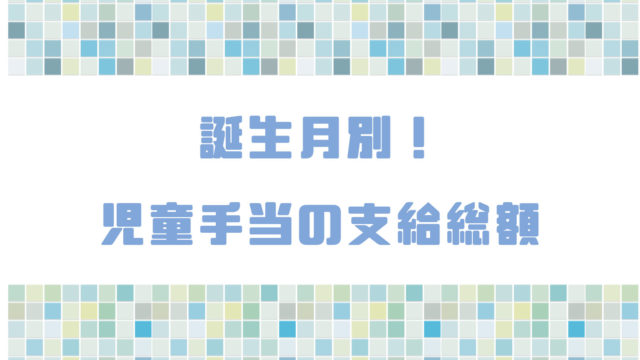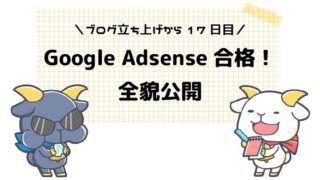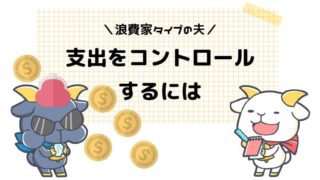高額療養費制度とは?医療費が返って来る場合もあることを知っておこう

入院や手術をすると、ものすごくお金がかかるのでは?と不安になります。
医療保険に入ってなかったり、入っていても適当に何となくで入っていたら、もっとちゃんと調べて入っておくべきだった!と感じますよね。
実際、私も妊娠中に入院・手術をして、お金がものすごくかかったらどうしよう?という不安に駆られました。
でも実は、一旦高額な医療費を払わないといけなくても、一部は戻ってくる場合があるんです。
それが「高額療養費制度」です。
手続きは加入している健康保険組合によるんですが、自動で計算して口座に振り込んでくれる事が多いです。
今回は、高額療養費制度がどんな制度なのか詳しく見ていきましょう。
高額療養費制度とは
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
引用-厚生労働省HP
なお、この「窓口で支払った額」に入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
医療費の支払いの上限額はいくら?
医療費の支払いの上限額は、年齢や所得によって異なります。
69歳以下の人の場合
| 適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) | |
| ア | 年収約1,160万円 | 252,600円+(医療費-842,000)×1% |
| イ | 年収約770~1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% |
| ウ | 年収約370~770万円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% |
| エ | ~年収約370万円 | 57,600円 |
| オ | 住民税非課税者 | 35,400円 |
70歳以下の人の場合
| 適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) | ||
| 外来(個人ごと) | |||
| 現役並み | 年収約1,160万円 | 252,600円+(医療費-842,000)×1% | |
| 年収約770~1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% | ||
| 年収約370~770万円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% | ||
| 一般 | 年収約156~370万円 | 18,000円 (年14万4千円) | 57,600円 |
| 住民税 非課税等 | Ⅱ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
| Ⅰ 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) | 15,000円 | ||
表の医療費は、すべての医療費の合算額です。
1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含む)では上限額を超えなくても、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は21,000円以上であることが必要)を合算することができます。
この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
さらに医療費の負担を軽減するには?
医療費の負担を軽減するために、こんな仕組みもあります。
- 世帯合算
- 多数回該当
順番に、どのような内容なのか見ていきましょう。
世帯合算
同一世帯で医療費をいっぱい払った場合には合算できます。
一人あたり1回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯にいる他の人(同じ保険に加入している方に限る)の受診について、窓口でそれぞれ支払った自己負担額を一ヶ月単位で合算することができます。
その合算額が一定額を超えたときは、超えた分を高額療養費として支給されます。ただし、69歳以下の方は、21,000円以上の自己負担のみ合算可能。
同一世帯と言いつつ、共働きで別々の健康保険に入っていると合算できないってことですね。
多数回該当
過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、医療費負担の上限額が下がります。
| 所得区分 | 多数回該当の場合 |
| 年収約1,160万円 | 140,100円 |
| 年収約770~1,160万円 | 93,000円 |
| 年収約370~770万円 | 44,400円 |
| ~年収約370万円 | 44,400円 |
| 住民税非課税者 | 24,600円(※) |
※70歳以上の場合は適用なし
まとめ:医療費には限度額がある(高額療養費制度)ので、窓口でいっぱい払っても戻ってくる
高額療養費制度で医療費の上限は決まっているため、たくさん支払ったとしても限度額を超えていれば戻ってくるのでご安心を。
また、加入している健康保険によっては、更に自己負担を軽減するために付加金が出る場合もあります。
入院などで多額の医療費を支払う必要が出てきたら、まずは自分の入っている健康保険組合に、制度の詳細を確認しておくといいですよ。
妊娠中の医療費や入院関連の話は、「子宮頸管無力症、体験記。まとめ」にまとめていますので、良ければそちらも読んでみてくださいね!